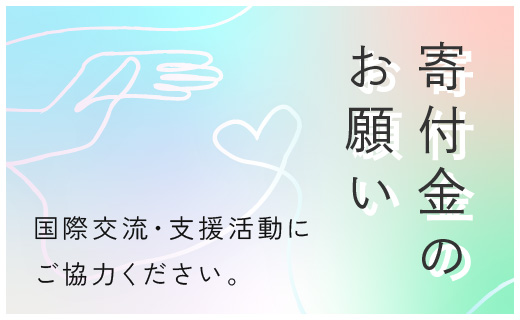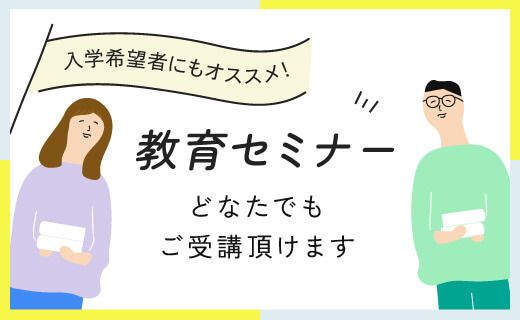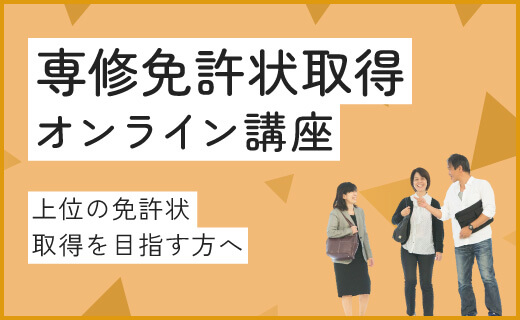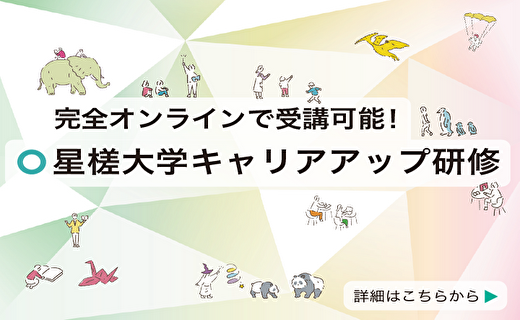2025.03.24
専門職学位課程修了生の松山綾子さんが日本保育者養成教育学会第9回研究大会にてポスター発表を行いました
専門職学位課程修了生の松山綾子さんが日本保育者養成教育学会の日本保育者養成教育学会第9回研究大会にてポスター発表を行いました。(専門職学位課程修了生の三友玲子さんは共同発表者)
タイトル: 保育実習Ⅱ ( 保育所 ) における学生の自己肯定感について
概要:
【はじめに】
保育者養成校において保育士資格取得のためには事前事後指導に加え、保育実習Ⅰでは保育所および施設に各施設90時間以上かつ10日以上に加え、保育実習Ⅱ(保育所)または保育実習Ⅲ(施設)を選択した上で90時間以上かつ10日以上実務実習に行くことが義務付けられている。すでに2回以上の実習を終えている学生が、実習を通してどのように自己肯定感を養ったかということについて検討する。
【方法】
・期間:2024年4月5日(金)~2025年1月10日(金)
・前期および後期の2期(30コマ/前期15、後期15コマ)
・前期/4~8月、金曜日1時限目(9:00~10:30)
・後期/9~1月、金曜日3時限目(13:00~14:30)
・対象者:A短期大学こども教育学科に在籍の2年生、12名、(男子4名、女子8名)
・授業内容:指導教育内容は保育実習Ⅱ(保育所)の事前指導として、保育実習における模擬日誌の作成、保育所における模擬実習、部分実習指導案作成および指導、保育所の指導者観点についてなどを学んだ後、事後指導にてインタビューおよび自己肯定感に関する事後報告書の作成、提出書類の添削指導を行った。
【結果】
1)実習事前指導において初期には学生からは実習を楽しめる気がしない・実習に行くことが怖いと言う意見が聞かれた。これらについては、実習指導Ⅰおいて学びが少ないと実習園において指摘をされたことが心に残っているとのことであった。また、これらの学生(12名中9名)については、施設からの評価と学生の評価に大きな差はみられず、施設からの評価と同等か近似値であった。
2)施設との自己評価が乖離している学生について
3パターンあり、①実習が楽しみという学生(A学生)については自己肯定感が非常に強い。(自己評価については、すべての項目が5)。同学生は実習および普段の学生生活の行動観察では、常に「自分の行うことが正しい」
と信じている傾向が見られた。
②すべての項目に対して、ほぼ4または5と感じている学生(B学生)については、実習前に特に不安を訴えることはなかった。園からの成績については5段段階の評価では、2(努力を要する)であり、自己評価との大きな乖離が見られた。また同学生は、普段は寡黙であるものの、学生自身に対する指摘事項(落ち度など)や、他者の落ち度については強くものを申す姿(いわゆるマウント取り)が見られる。
3)一方、自己肯定感が非常に低いと感じている学生(すべての項目において2または3以下)については、常に授業でも寡黙であり、教師から指導案などについて指摘をされると、うつむいて黙る傾向や、指摘されたことに対して②の学生同様、他者を許さない傾向が見られた。
【考察】
学生の実習に対する苦手意識の原因(要素)の一つとして、学生が教師以外の大人からの評価(点数化)を受けることが少なかったことが聞き取り調査で明らかになった。子どもに対しては恐怖心をもつ学生は少なく、子どもの前で手遊びや読み聞かせを行うことは怖くないと言う学生が多くいた。これらのことから、学生は保育者を「大人」であり「採点者」であると捉えているのではないだろうかと考えられる。
自己肯定感は非常に大切である。自己肯定感を含む保育者の等身大の保育観が子どもや同僚などヘ言動として顕著に表れる。しかし一方で、自己肯定感が高すぎても低すぎても、等身大の自己が見えていないため、他者に対して適切な行動を起こすことが難しくなる。
さらに自己肯定感が極端に高いまたは低いと感じている学生は、子どもに対しては自らと「同等以下」とみなす、または「非採点者」であるという意識の表れか、子どもに対して高圧的または強い口調で接するなどの不適切保育に近い状態や、実習生として好ましくないと感じられる実習の様子が実習巡回指導(学生の行動観察)および実習園からの聞き取り)の中で垣間見えていた。そのような中、学校ではなく「保育所」と言う別のフィールド/外部社会で評価をされることは学生にとって等身大の自己を見つめ直す契機となる。
さらに成績ではなく、自分自身の力量を冷静に見つめ直す省察を行うことにより、適切な自己肯定感を養うことが可能である。この結果、学生は保育実習を通じて等身大の自己肯定感を養うことにより、自己を正しく見つめることが出来るだけでなく、自らの保育観についても省察することが出来るのである。