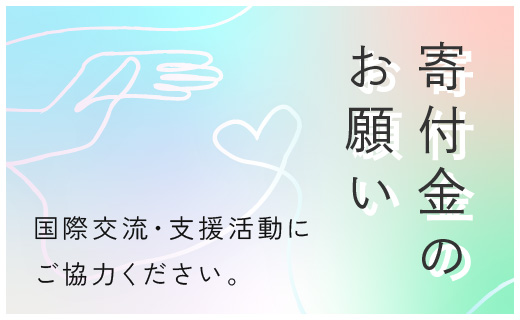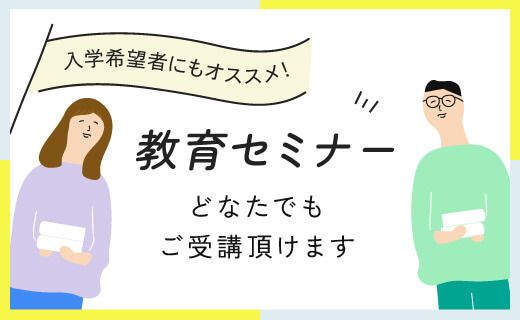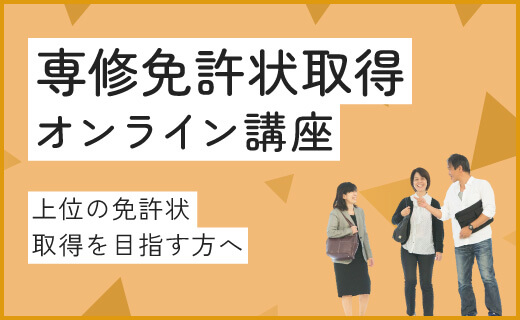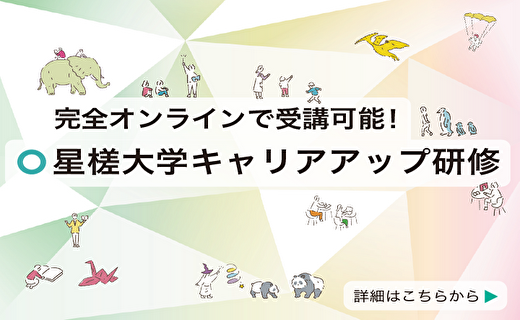2025.11.27
松山綾子さん(本学専門職学位課程修了生)が環境福祉学会第21回年次大会にて口頭発表を行いました。
【タイトル】日本における相対的貧困と子どもへの影響について
【概要】貧困には、①食事がとれない・住む家がない等、命の危機に直接関わるいわゆる「絶対的貧困」と、②住む場所などは確保できているものの食事に不自由をするなど、見かけだけでは分かりにくい「相対的貧困」がある。絶対的貧困は外見(時季外れの服装や清潔さに欠ける等)から理解が可能だが、相対的貧困は外見での理解は難しい。
相対的貧困はその国や地域の水準の中で比較し、大多数よりも貧しい状態であり、所得で見ると世帯所得がその国の等価可処分所得の中央値の半分(いわゆる貧困線)に満たないためであり、先に述べたように命の危険性がすぐに差し迫っていないからである。「子どもの貧困」は2023年7月4日に厚生労働省が公表した「国民生活基礎調査」によると子どもの貧困率は、2018年では14.0%、2021年は15.1%、と最悪であった2012年の16.3%よりは若干低下はしているものの、ほぼ横ばいである。貧困の原因は、地域としての共同力の低下や、少子高齢化による親戚づきあいの希薄さ、家族力の低下などが挙げられる。また相対的貧困者には、ひとり親家庭が多くみられる。
このような中、子ども家庭庁では、子ども自身が本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行い、家庭を支えるために本来であれば子どもとして享受できる勉強や部活動に励む時間、余暇等「子どもとしての時間を引き換え」つまり自己犠牲を払う「ヤングケアラー」問題に注目し、子ども自身に対する影響について検討した。
当日の研究発表一覧はこちらからご覧ください。