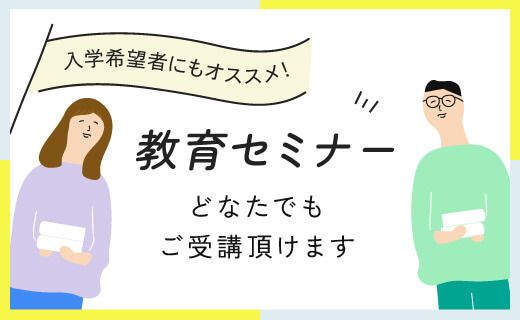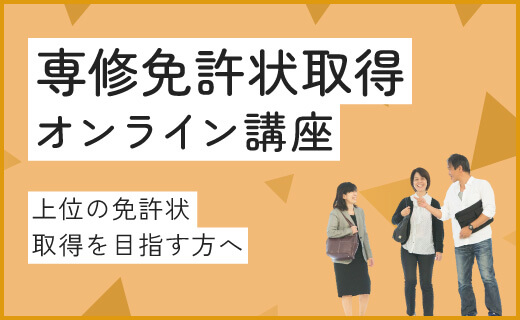2022.09.14
自然環境や多民族との“共生”の根拠を問う〜先住民族の視点から(1)
「共に生きる」ということ
「その黒いアリに噛まれる(かまれる)と痛いぞ」と先住民族ピグミーに教わる。コンゴ共和国北東部の原生林を先住民族ピグミーと歩いていたときのことである。よく見ると、体長が1cmほどもある何匹もの黒アリが小さな木の根っこの周りをうろうろしている。その木にも上っていて、幹や枝の先端までその多くが歩き回っていた。そのピグミーは「木でも触ろうものならパンボはすぐに噛みつきに来るぜ!」とぼくに警告する。この植物は現地語で“パンボ”と呼ばれるその黒アリに枝の中の一部を巣として提供している、その代わり、パンボは植物の葉などを食べに来る小動物や昆虫を鋭い鎌で噛み付いて追い払いまた退治するとピグミーから教わる。
これが生態学でいうところの「共利共生」という生物種同士の関係の一つだなと思い当たる。生態学など学んだことのないピグミーは、長年に渡る森の中での経験と伝統知から野生生物種同士の関係を理解していると言える。異なる生物が「共に生きている」現場を十全に知っているのだ。
こうした「共に生きている」両者には優劣も格差もない。その関係性は「対等」であると言えるし「微妙なバランス」と呼んでもいいのかもしれない。両者とは独立した「第三者」のみがその関係性を客観的に捉えられる。外部「観察者」としての生態学者がそれを「共生」と称する。生態学者ではないピグミーは「共生」という概念はなくそのことばすら彼らの言語になくても、伝統知に基づいた「共に生きる実態」として見事に認識していると言える。ぼく自身もそれを教科書ではなくピグミーから学んだのだ。
オレたちの森を返してくれ…
ある場所を先住の土地として長年に渡り済み続けてきた先住民族は、開拓や資源開発ほか環境保全や学校教育など多様なプロジェクトの名目で外部から入植してきた資本を持つ支配者民族に追い出されてきた。とりわけ開発事業は先住民族への経済支援を謳う(うたう)と同時に、彼らがもともと依拠してきた自然界を消失させるということでもあり、そこでの狩猟採集といった伝統的生活様式や動植物など自然界に関する伝統知の喪失にも繋がる(つながる)。
一方、学術目的とはいえ外部から入ってきた研究者は先住民族そのものを、あるいはその骨や血液を含む身体や文化遺品をも「研究対象」としてきた。そこには学術を正当化する基盤から、「上から下目線」の発想が無意識的にでも働いている場合も否めない。また野生生物の研究者が自然界をよく知る先住民族を研究アシスタントとして雇ったり、エコツアーこそが自然環境保全と経済の両立を可能にするという考えから先住民族を雇ったりした結果、彼らコミュニティーの内部で従来存在しなかった経済的格差を作ってきている事例は枚挙にいとまがない。
また、野生生物保全や森林保全は地球規模で第一義的に大事だとの主張のもと、外部の人間が国立公園や保護区を制定することは多々ある。しかしその結果、元来その土地に住んできた先住民族への土地侵害や人権侵害をもたらしてきたことも少なくない。
そして、いまやどんな奥地にも学校が建てられ、公用語ほか算数など初等教育が提供されている。「識字率を上げる」ことが第一義的に重要と考える国際支援プロジェクトなどがそれをサポートする。ところが先住民族が每日学校に通わざるを得ない事態は、本来彼らが依拠してきた自然界での生活様式との乖離(かいり)をもたらし、世代を通じて継承されてきた自然に関する伝統知が失われる結果を現実的にもたらしている。さらに、支配者民族の子供と同じ教室にいざるを得ない先住民族の子供はそこでいじめに会い差別を受ける。
年長のピグミーのひとりは「外部からいろいろな連中がやってきてはなんだかんだ言って来ているけど…はっきり言ってどうでもいい!オレたちの森を返してくれ」と言う。「(今の貨幣経済の中)お金はある程度必要だけど、オレたちが依存してきた動物や植物はいったいどこへいってしまったのだ」と嘆く。そして「子どもたちが学校に行っていろいろ学ぶのはよしとしても、もうオレたちの伝統的な知恵は継承されなくなるんだよな…子どもたちのこれからが心配だ」と嘆く。
こうした事態は、先住民族と「共に生きていく」共生社会とは相容れない現状であると言えまいか。いずれも、資本を持つ支配者民族である当事者が一方的に彼らと先住民族との「共生」を「上から下目線」で目指そうとしているからではないか。そこには独立した「第三者視点」が決定的にない(続)。
本小論は2022年6月4日に開催された「第14回日本共生科学会(オンライン大会)」でのシンポジウム「人と国際社会との共生―その課題と展望を探る」にて、シンポジストとして同じ題名で筆者が話題提供をした内容をベースにして書き下ろしたものである。