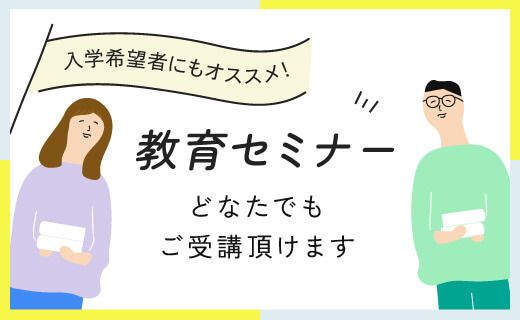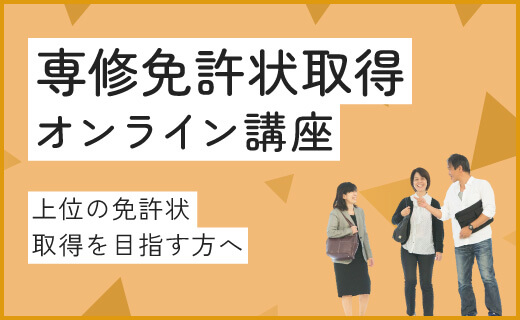2022.09.15
自然環境や多民族との“共生”の根拠を問う〜先住民族の視点から(2)
当事者が述べる「共生」の是非
社会科学の分野でも「共生」ということばが転用されて以来、人間同士の格差や差別をなくしていく社会を目標としていくことが人類の大きな課題となっている。「ひとりも残さない」をモットーとするSDGsに触発されてか、「共生社会」の実現は人類社会にとってキーワードのひとつになっている。
ピグミーのような先住民族との「共生」はその中でも重要項目と言っていい。特に近現代の歴史の中で、世界中の先住民族は支配者民族あるいは国家から差別を受け、土地や文化、言語をも奪われ、甚大な人権侵害を受けてきたからだ。もともと国家の存在とは無縁に自然環境に依拠してきた先住民族は、強制移住や民族の分断なども経験してきている。そうした過去を顧みて先住民族の権利回復のために、国連も2007年に「先住民族の権利に関する国際連合宣言」を採択し多くの国が批准した。先住民族がこれまでの被差別の対象ではなくこの地球上で対等に生きていけるような、まさに「共生社会」の実現に向けた画期的な宣言といってもいい。
北海道・白老には、日本ではじめての国立の先住民族博物館「ウポポイ」が開館した。「民族共生象徴空間」と名付けられている。それが和人と先住民族アイヌとの間の「共生」を象徴する場所であるというのだ。まるで「民族共生社会」の実現の場であるかのような印象を与えている。ところが実際は、その博物館があっても、日本も批准した「先住民族の権利に関する国際連合宣言」で約束されたはずのアイヌ民族への権利回復には程遠く、しかもそこで展示されている和人とアイヌ民族との間で起こった歴史記述についても和人の一方的な視点からの記述が顕著に見られる。博物館の名前とは別に「民族共生」とは大きくかけ離れているのである。
「共生」という言葉が、社会的強者である和人側から発せられている点が問題なのである。ここでも客観的に判断できる「第三者」ではなく「当事者」が「共生」という言葉を発するところに無理があると考えられる。
「気候正義」との関わりで
地球規模の気候変動が現実化している中、「気候正義」の実現こそが重要課題だと唱えられてきている。
(1)1人当たりの温室効果ガス排出量が小さい途上国の人々が、1人当たりの温室効果ガス排出量が大きい先進国の人々よりも、より大きな気候変動による被害を受ける;
(2)先進国の中でも、貧困層、先住民、有色人種、女性、子供がより大きな被害を受ける;
(3)未来世代がより大きな被害を受ける、といったようなことは「不正義」であるからそうでない「正義」を目指すべきだと語られる。長い年月にわたり社会的弱者であった、しかも途上国に多い先住民族が気候変動による被害をより深刻に受ける可能性は確かであろう。だからこそ、そうならないための「気候正義」が地球規模で必要なのである。
温室効果ガス排出の元凶である化石燃料の利用の抑制と放射性物質と常に隣り合わせの原子力発電に代わるものとして、自然再生エネルギーや蓄電池、電気自動車の開発・普及が促進されているのは周知のとおりである。しかしながら、再生可能エネルギーや電気自動車などハイテク製品開発による気候変動緩和の実現には、これまで以上に地球上の希少金属などが必須となり、その開発は一層加速度化されている現状がある。そうした地下資源は熱帯林地域に多く、その採掘のために熱帯林という自然環境は破壊され、そこに依拠してきた先住民族は従来からの居住場所を失う。こうした事態は民族「共生社会」とは相反するものではないか。自然との「共生」とも相克する事態が蔓延(まんえん)している。
国土の狭い日本では巨大再生可能エネルギーは人口密度の低い地方に設置され、それが都市で売電され都市での温室効果ガス排出削減に繋げる(つなげる)という政策がある。これを環境省は「地域循環共生圏」と称した。ところが実際は、地方で自然環境が破壊され絶滅危惧種を含み生物多様性は喪失、土砂崩れの危険性や景観被害などが生み出されている。「共生」とは名ばかりで、これも「第三者」視点を欠いた、地方を十全に配慮しない経済的強者である都市圏中心の当事者発想である点が問われる。昨今は、先住民族の住む土地に事前協議もなくこうした再生エネルギーが設置される事例が海外では目立つようになってきており、ここでも先住民族との「共生社会」とは縁遠いものとなっている。
気候変動対策は温室効果ガス削減だけではないはずである。自然界や多民族との「共生」に大きな課題を残している新規ビジネスとしての再生可能エネルギーや電気自動車の開発は、真の意味での「気候正義」を目指す上で再検討の余地があるだろう。なによりも温室効果ガスの吸収源である自然環境の保全とその自然環境を担保する生物多様性保全、そしてその自然環境で長大な歴史を通じて永続的な保全を担ってきた先住民族と彼らの知恵の継承と人権の回復をまずは念頭に置くべきであろう。環境NGOなどに見られるような過剰な再生可能エネルギーや電気自動車の普及キャンペーンは、「気候正義」と称して行われているケースが少なからず見られる。しかし、先住民族や地方の住民(日本の場合)などの社会的/経済的弱者や自然界が犠牲になっているとしたら「気候正義」とは言えないであろう。
本小論は2022年6月4日に開催された「第14回日本共生科学会(オンライン大会)」でのシンポジウム「人と国際社会との共生―その課題と展望を探る」にて、シンポジストとして同じ題名で筆者が話題提供をした内容をベースにして書き下ろしたものである。