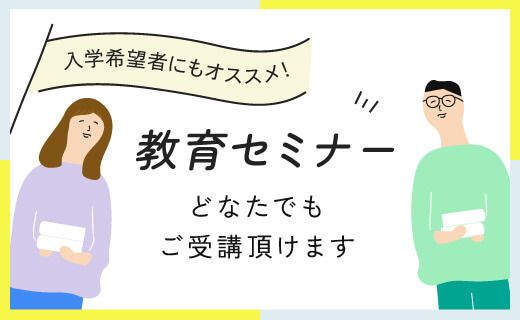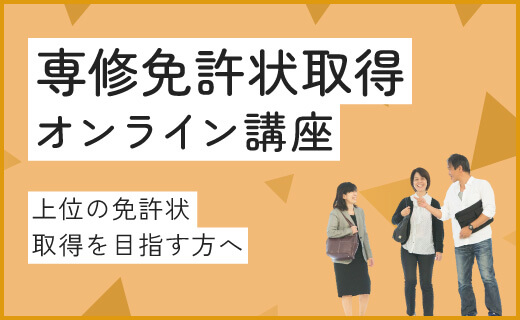2023.09.21
評論 「オスロ合意から30年」 ◎和平交渉の原点に戻れ ー共生の希望失うなー
パレスチナ紛争解決の土台と期待されたオスロ合意から30年が経過した。しかし合意は事実上破綻、イスラエルとパレスチナの対立が激化し、和平の展望は絶望的だ。合意にこぎつけたのはイスラエル、パレスチナの指導者らが紛争をなんとか解決しようと強い意思と勇気を持ち、互いに歩み寄ったからだ。今こそ双方は合意当時の交渉の原点に戻り、中東和平実現に向け再出発すべきだ。
オスロ合意は1993年、ノルウェーの仲介でイスラエルとパレスチナが秘密交渉を行い、米国の側面支援でまとまった。和平の道筋とパレスチナの将来像を示した意味で画期的だった。30年前の9月13日。ホワイトハウスのローズガーデンの式典にはクリントン米大統領が真ん中に立ち、イスラエルのラビン首相とパレスチナ解放機構(PLO)のアラファト議長が向かい合い、おずおずと握手を交わした。長年の敵意と憎悪が友好と希望に転換した瞬間だった。カイロから取材に飛んできた私は少なくともそう思い、そんな記事を東京に送った。
内容はイスラエル占領下のヨルダン川西岸とガザにパレスチナ自治区をまず作り、最終的には当地に独立国家を樹立、イスラエルとの「2国家共存」による恒久和平を実現する手順だった。
しかし、その後の交渉は聖地エルサレムの帰属、難民の帰還、独立国家の権限、境界の確定などの対立点をめぐって暗礁に乗り上げ頓挫した。ラビン首相は暗殺され、アラファト議長も今はない。毒殺されたという説も消えていない。交渉がストップする中、西岸へのユダヤ人入植地が拡大、進展しない交渉に対するパレスチナ人の不満と怒りが高まっていった。
背景にはイスラエルに、西岸の併合を主張する対パレスチナ強硬派のネタニヤフ右派政権が断続的に続いたことがあるが、中東地域の政治環境や意識の変化も大きい。
その最たるものはパレスチナの地をアラブ人の手に取り戻すという「大義」がアラブ世界から消えつつあることだ。アラブ諸国にとってイスラエルは戦後、4度の中東戦争を戦った敵国だった。
だが、紛争が長期化するにつれ、アラブ各国のイスラエルに対する敵対意識が軟化。イスラエルと国交を持つ国は当初のエジプト、ヨルダンにアラブ首長国連邦(UAE)など3カ国が加わった。当面はアラブの大国サウジアラビアがイスラエルとの関係正常化に踏み切るかが最大の焦点だ。
もう1つは米国が和平の芽を摘んだことだ。歴代の米政権は中立的な調停者の立場を堅持してきたが、トランプ前政権はエルサレムをイスラエルの首都と認定、自治区の面積を大幅に削ったイスラエル寄りの和平案を提示、パレスチナ側が完全に離反してしまった。
今年に入ってパレスチナ人のユダヤ人襲撃とイスラエル軍の報復が相次ぎ、緊張が続いたままだ。こうした暴力の連鎖はなんとしても止めなければならない。国際社会はイスラエル、パレスチナ双方に対し、和平交渉を再開するよう強く説得すべきだ。パレスチナの地に両民族が共生する希望を失ってはなるまい。